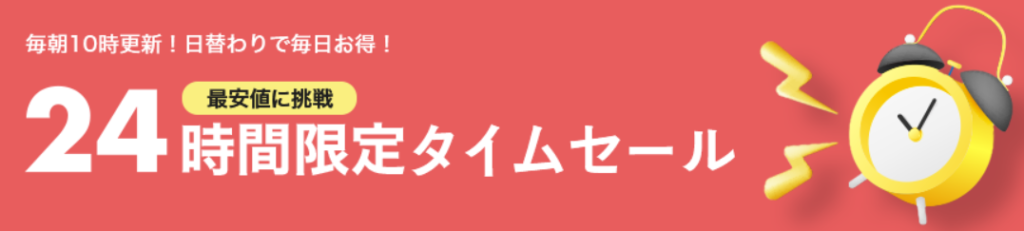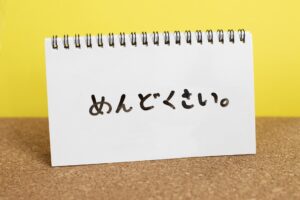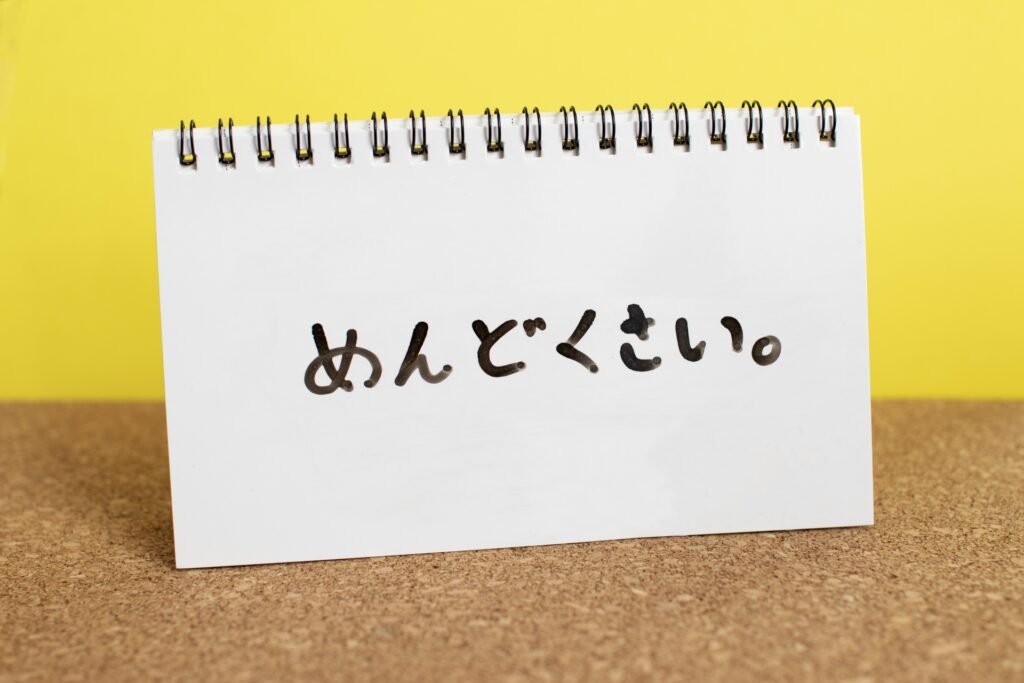
「退職プレゼントめんどくさい」と感じて検索されているあなた、お気持ちよくわかります。職場の慣習や空気感って、正直なところすごく気を使いますよね。特に「退職する人へのプレゼントをあげないなんて非常識?」と悩んだり、「退職プレゼントが迷惑って思われることもあるの?」と戸惑ったり…日々の仕事だけでも大変なのに、こうした“お付き合い”にまで気を遣うのは本当にしんどいものです。
今回の記事では、退職者への餞別をあげたくないと感じた瞬間や、プレゼントは個人的に渡してもいいの?といった素朴な疑問を始め、「退職プレゼントはみんなで用意するべきなのか」「自己都合退職のときも何か渡すべきか」など、よくあるシーン別に丁寧に解説していきます。
また、「退職する人へのプレゼント、女性には何が喜ばれる?」「男性にはどんなものが定番?」といったお悩みへのヒントや、「実は何も貰えなかった…」という方の本音、「センスのいい退職祝いとは?」「あげてはいけないNGギフトとは?」などの気になるポイントもカバーしています。
「退職プレゼントはもういらないかも…」と感じている方が、どうやって負担なく、角を立てずに断れるか。そんなリアルな課題に向き合いながら、“無理せずちょうどよくやり過ごす方法”を、一緒に見つけていきましょう。
- プレゼントを渡さない選択が必ずしも非常識ではないこと
- 退職プレゼントを迷惑に感じる人の本音と理由
- 有志参加や個人での対応など柔軟な方法があること
- あげるべきでないNGプレゼントの具体例
退職プレゼントめんどくさいと感じる理由とは

退職する人へのプレゼントをあげないのは非常識?
必ずしも非常識とは限りません。
むしろ、状況によっては「配慮がある行動」と捉えられることもあります。
このテーマを考えるうえで大切なのは、「職場ごとの慣習」と「退職者との関係性」です。
昔からの慣習でプレゼントを渡す職場であれば、あげない選択が浮いてしまう可能性もあります。ですが、全員が毎回あげているわけではない、または「有志のみ」や「親しい人だけで渡す」という風土であれば、渡さないことがとくに問題視されることは少ないです。
例えば、退職者と業務でほとんど関わりがなかった場合や、短期間しか在籍していなかった人に対しては、「お世話になったわけではないし…」と感じるのも自然なことです。このようなケースで無理に渡しても、形式的で心のこもらないプレゼントになってしまいます。
また、「退職祝いは有志で行う」と事前に案内されているにもかかわらず、「強制的な徴収」や「内容が不透明なプレゼント」がある場合、あえて断る方が誠実な対応とも言えるかもしれません。
とはいえ、感謝の気持ちを形にする場でもあるため、気まずくならないようにするには、事前に周囲と意思をすり合わせることがポイントです。可能であれば、「私は今回は気持ちだけで…」と伝えると角も立ちにくくなります。
つまり、退職する人へのプレゼントをあげないからといって、一律で非常識とされることはありません。
大切なのは、相手への思いやりと、周囲とのコミュニケーションです。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
▼小さな缶に感謝を込めて▼
退職プレゼントを迷惑と感じる人の声
実は退職プレゼントを「ありがた迷惑」と感じている人も少なくありません。
その理由には、いくつか共通した傾向があります。
まず多いのは、「好みに合わない物をもらっても困る」という声です。
特にコスメや雑貨、小物類などは人によって好みが分かれるため、使わないまま処分に困ってしまうことも。
「せっかくもらったのに捨てられない」という気持ちから、かえってストレスに感じる方もいらっしゃいます。
また、「荷物が増えるのが面倒」という声もあります。退職当日は私物の整理や引き継ぎ対応などでバタバタしがちです。花束や大きな品物は持ち帰りづらく、荷物になることに対してネガティブな印象を持つ人もいます。
さらに、「プレゼントをもらうとお返しをしなきゃいけない」というプレッシャーを感じるケースも。特に退職後すぐに新しい環境へ移る人や、プライベートが忙しい人にとっては、内心負担に思うこともあるようです。
例えば、「気持ちだけで十分だから、何もいらないというのが本音です」という退職経験者の声もあります。
つまり、退職プレゼントは必ずしも喜ばれるものではないということです。
このように、形式的な贈り物がかえって相手の負担になることもあります。もし迷ったときは、ギフトカードやメッセージカードのように、かさばらず実用的なものを検討するのがよいでしょう。あるいは、あえて「何か必要なものある?」と本人に聞いてしまうのも、スマートな方法です。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
退職者に餞別をあげたくないと思う瞬間
餞別は「お世話になった感謝の気持ち」として贈るものですが、あげたくないと思ってしまう瞬間は誰にでもあるものです。それが非常識というわけではありません。
まず一番多いのは、「ほとんど話したことがない相手が退職するとき」です。業務上のやり取りがほぼなく、名前や顔もうろ覚えな場合に、無理にお金を出してまで餞別を用意することに疑問を持つ方は多いです。
また、「強制的に徴収されるケース」も悩みのタネになりがちです。たとえば、何の相談もなく「○○さんの餞別代として一人500円お願いします」と連絡が来るパターンですね。参加するかどうかの選択肢がないことにモヤモヤする方も少なくありません。
さらに、「何度も退職者が出て、出費がかさむ時期」も、あげたくない気持ちが強くなる場面です。毎回500円でも、1か月に何人も辞めれば結構な負担になります。特に扶養内で働いている方や、家庭の支出が多い方にとっては深刻です。
そしてもう一つ、「主導する人のやり方が納得いかないとき」もあります。贈る品を勝手に決められたり、高額なものを買われてから「後で割り勘ね」と言われたりすると、不満が出やすくなります。
つまり、餞別をあげたくない瞬間は、金額よりも“気持ちの納得感”がないときに生まれやすいということなんです。
誰にでもある正直な気持ちなので、まずは自分の感覚を否定せずに、「どこにひっかかりがあるのか」を整理してみるのがよいと思いますよ。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
▼上品なお茶時間を贈る▼
退職 何も貰えなかったときの本音
実際に「退職するとき、何ももらえなかった…」という経験をすると、少なからず寂しさや虚しさを感じる人が多いようです。
とくに周囲の人が花束やプレゼントをもらっていたのを見ていると、自分だけ何もない状況にショックを受けることもあります。
たとえば、「一生懸命働いてきたのに」「それなりにチームに貢献したはずなのに」と思っている場合、期待が裏切られたような気持ちになりやすいです。
これは金額や品物の問題ではなく、“感謝の気持ちを形にしてもらえなかった”ことが心に残るんですね。
一方で、「仕方ない」と割り切る人もいます。例えば、職場にそういった慣習がなかった、人数が多くて誰が退職するか把握されていなかった、などの背景があると、「気づかれなかっただけ」と考えることで気持ちを整理する人もいます。
ただし、本音では「少しでいいから気持ちが欲しかった」「一言でもありがとうと言ってもらえたらよかった」と感じているケースがほとんどです。
このような経験をすると、逆に自分が贈る立場になったとき、「自分はそうならないようにしよう」と行動を変えるきっかけになることもあります。
つまり、「何も貰えなかった」という事実は小さなことのように見えて、働いてきた自分の存在がどう扱われたか、というメッセージに感じてしまうというわけです。
職場全体でその点に無関心な雰囲気があるとすれば、「人を大事にしない職場」だと感じて退職を後悔する人も出てきます。
それくらい、退職時のやりとりは小さく見えても、心に残るものなのです。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
退職 プレゼントを個人的に渡すのはアリ?
はい、退職プレゼントを個人的に渡すのはもちろん「アリ」な選択肢です。ただし、ちょっとした配慮が必要です。贈ること自体に問題はありませんが、タイミングや渡し方、まわりへの気配りを忘れてはいけません。
まず、個人的に渡すことで生まれるメリットはたくさんあります。たとえば、「本当にお世話になった方に自分の言葉で感謝を伝えたい」と思ったとき、みんなで贈る形式だと気持ちがぼやけてしまうこともありますよね。
そういったときには、ちょっとしたメッセージカードと一緒にプチギフトを渡すと、とても心がこもった印象になります。
一方で、注意点もあります。それは、「あの人には個人的にもプレゼントがあったのに、自分にはなかった…」と、他の人が感じてしまう可能性があることです。特に少人数の職場やチーム内では、意外と見られているものです。
このリスクを避けたい場合は、できるだけ人目につかないタイミングで渡すのがベストです。たとえば、最終日の終業後に声をかける、ランチの時間にそっと渡すなどの工夫が大切になります。
また、「あなただけに渡すのが申し訳ない気がして…」といった一言を添えるだけでも、気まずさを和らげる効果があります。心を込めた行動であれば、相手にもきっと伝わります。
このように、「個人的に渡すのはアリだけど、ちょっとだけ気をつけて」というのが現実的なアドバイスです。無理して全員に合わせる必要はありませんが、思いやりと空気を読む力のバランスが、スマートな印象につながっていきます。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
▼見た目も味もスマートに▼
退職プレゼントめんどくさいときの対処法

退職する人へのプレゼント 女性に人気の品
女性への退職プレゼントは、「おしゃれで気が利いている」ことがポイントになります。とはいえ、相手の好みが分からないケースも多いため、万人受けする実用的なアイテムが喜ばれる傾向にあります。
具体的に人気なのは、まず花束やフラワーアレンジメントです。見た目が華やかで、「お疲れさまでした」という気持ちを視覚的に伝えられますし、写真映えするのも理由のひとつです。花は軽くてかさばらないため、持ち帰りやすさもポイントです。
また、スイーツや紅茶、コーヒーなどの「消えもの」系ギフトも鉄板です。おしゃれなパッケージのものを選べば、受け取った側も気分が上がりますよね。「好みに合わなかったらどうしよう…」と迷うなら、カタログギフトやギフトカードも無難で安心です。
さらに最近では、ちょっとしたコスメやハンドクリームなどの美容系アイテムも人気です。ただし、肌に直接使うものは好みやアレルギーが関係するので、避けたほうが無難なケースもあります。
大事なのは、「ありがとう」と「お疲れさま」を伝える気持ちが形になっていること。相手が受け取りやすく、気を使わせないようなサイズ感・予算感・タイミングを考えて選ぶのが、スマートなプレゼント選びになります。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
退職する人へのプレゼント 男性には何が定番?
男性への退職プレゼント選びは、「実用性」と「気軽さ」のバランスが大切です。職場の関係性があっさりしていることも多く、あまり気を遣わせないアイテムが喜ばれる傾向にあります。
定番としてまず挙げられるのが、お菓子やドリップコーヒーなどの消えものです。特に、個包装になっているものや有名ブランドの詰め合わせなら、品の良さもあって安心して渡せます。「重くない、気楽に受け取れる」がカギです。
次に多いのが、ギフトカードやカタログギフトです。趣味や好みが分からないときでも選ぶ楽しみがあり、「失敗しないプレゼント」として鉄板です。特に退職後の生活に使ってもらえるような自由度の高いプレゼントは、年代問わず人気があります。
もし個人的な関係性が深い場合は、ネクタイやボールペンなどのビジネスアイテムも選択肢に入ります。ただし、こういったアイテムは「個人的すぎる」と感じる人もいるので、必ず関係性を見極めることが大切です。
また、男性に香りもの(フレグランス系)を贈るのは基本的に避けたほうが無難です。使う習慣がない方も多く、好みが分かれるためトラブルの元になりがちです。
総じて、男性への退職プレゼントは「使いやすい」「気を使わせない」「感謝が伝わる」という3つのポイントを押さえることで、しっかり気持ちのこもった贈り物になりますよ。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
▼気軽に渡せる感謝の気持ち▼
自己都合退職 プレゼントは必要?
自己都合での退職となると、「プレゼントって渡すべき?」と悩むこと、ありますよね。実際、退職理由が個人的な事情である場合、贈り物の必要性に疑問を持つ方も少なくありません。
このようなケースでは、職場の慣習や退職者との関係性が判断の軸になります。職場で「退職=プレゼントを渡すのが当たり前」という文化が根づいていれば、自己都合でも何らかの贈り物を準備するのが無難です。一方で、贈るかどうかを「有志」で決めている職場であれば、渡さないという選択も自然です。
また、自己都合の理由がネガティブなもの(たとえば人間関係のトラブルや健康問題)である場合、「プレゼントをもらうのが逆に負担」になる方もいます。ですから、無理に渡すのではなく、「お疲れさまでした」という一言のほうが嬉しいと感じるケースも多いのです。
もし贈る場合は、高価なものではなく、気軽に受け取れる「お菓子」や「花束」などがおすすめです。形式的にならず、気持ちのこもったちょうどよい距離感が伝わります。
このように考えると、自己都合退職のときは、「贈らなければ非常識」ということではなく、場に応じて判断する柔軟さが大切だと思います。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
退職 プレゼントをみんなで贈るときの注意点
退職プレゼントを「みんなで」用意する場合、気をつけたいのは「全員が納得できる形にすること」です。人数が多くなるほど、価値観の違いや関係性の温度差が出やすいので、ちょっとした配慮が必要になります。
まずは、「有志なのか、全員参加なのか」を最初にしっかり確認することが大切です。強制参加のような雰囲気になると、モヤモヤが残り、プレゼントそのものの価値が下がってしまいます。「出したくない人は遠慮なくパスしてくださいね」と一言添えると空気が和らぎます。
次に注意したいのは、「金額と内容のバランス」です。高すぎると負担に感じる人が出ますし、安すぎると形式的に見えてしまうことも。一般的には1人500円~1,000円以内で、消えもの+ちょっとした記念品のセットが好印象です。
さらに、「誰が買うか」「誰が渡すか」などの役割分担を明確にしておくことも重要です。段取りが曖昧だと、準備の段階でストレスが生まれやすくなります。特に代表でお金を集める人には、感謝の言葉を忘れずに伝えるようにしましょう。
最後に、渡すタイミングや場所にもひと工夫が必要です。業務の妨げにならない時間帯に、みんなが見守れる中で贈るのがベストです。その場にいない人にも後で報告できるよう、簡単なメモや写真を残すのもおすすめです。
このように、退職プレゼントをみんなで贈る場合は、「誰も無理せず、気持ちよく送り出せる形にする」ことが最大のポイントになります。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
▼ほっと一息つける贈り物▼
退職時にもらってうれしいプレゼントは何ですか?
これは人によってさまざまですが、アンケートや実際の声をもとにすると、「気軽に受け取れて、実用的なもの」が選ばれやすい傾向にあります。特に好評なのが、ギフトカードやお菓子、花束などの“消えもの”系です。
ギフトカードは、荷物にならず使い道も自由なので、退職時のバタバタしたときにもありがたいという声が多いです。次に人気なのが、焼き菓子やチョコレートなどのちょっとしたお菓子の詰め合わせ。こちらも食べれば無くなるので気軽ですし、価格的にも贈る側の負担が少なく済みます。
また、華やかさを添えたいときは花束もおすすめです。最近ではアレンジメントタイプやプリザーブドフラワーも増えていて、オフィスで渡すのにもぴったりです。ただし、相手が持ち帰る負担を考えて、小ぶりなサイズにするなどの気配りがあるとより喜ばれます。
一方で、高価すぎるものや趣味に寄りすぎたものは避けた方がベターです。「気を使わせたくない」「何を返せばいいかわからない」といったプレッシャーを与えてしまうこともあるためです。
つまり、退職時に喜ばれるのは、「気遣いが感じられて、もらっても気楽なもの」。気持ちのこもったちょっとした品に、手書きのメッセージを添えるだけでも、ぐっと印象が良くなりますよ。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
退職する人にあげてはいけないものは何ですか?
退職プレゼントを選ぶ際、つい気持ちが先走ってしまうこともありますが、注意すべきNGアイテムもいくつかあります。
まず避けたいのが、香水やフレグランスアイテムなど「香りが強いもの」です。これは好みが非常に分かれますし、アレルギーのリスクや、職場で使いづらいというケースもあるためです。
また、ハンカチや刃物類も、昔ながらのマナーでは“縁を切る”という意味合いがあるため、避けられる傾向があります。もちろん最近では気にしない人も増えていますが、無難に済ませたいなら避けておくと安心です。
さらに注意したいのは、名刺入れや文房具など、あからさまに「次の仕事を意識させるもの」。退職の理由が前向きであっても、今の職場からのプレゼントとしては場違いに感じられることがあります。
高額なブランド品も、やめておいたほうが無難です。受け取る側にプレッシャーを与えたり、「誰がいくら出したのか」で気まずい空気になる可能性があるためです。
このように、退職祝いは気持ちが大事とはいえ、「相手が受け取りやすいかどうか」を基準に考えることが何より大切です。迷ったときは、みんなが使えるギフトカードや、負担にならない消えものを選ぶと安心ですよ。
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
▼男女問わず喜ばれる定番▼
退職プレゼントめんどくさいと感じたときに知っておきたいことまとめ
- 退職プレゼントを渡さないのは必ずしも非常識ではない
- 職場の慣習や文化によって判断が分かれる
- 業務で関わりの少ない相手への贈り物は無理にしなくてよい
- 強制的な徴収がある場合は納得感が持てず不満になりやすい
- 気持ちがこもらない贈り物はむしろ逆効果になることもある
- プレゼントをありがた迷惑と感じる受け手も存在する
- 荷物が増えることを嫌がる人も多い
- お返しのプレッシャーで負担になるケースもある
- 餞別をあげたくないのは納得できない進め方にある
- 退職者が多い時期は費用がかさみ精神的にも負担になる
- 何ももらえなかった経験は思った以上に心に残る
- 個人的にプレゼントを渡すのはアリだが配慮が必要
- 女性には実用的かつおしゃれなアイテムが喜ばれる傾向
- 男性には消耗品やギフトカードなど気軽な品が定番
- 自己都合退職では場の空気を見ながら柔軟に対応すべき
参考
・退職プレゼントお礼LINEの基本と例文|送らないと失礼?タイミングとポイント
・嫌いな人退職プレゼントどうする? 渡すべきか 最低限のマナー
・退職プレゼント迷惑にならない配慮と負担にならない退職祝いの選び方
・送別会個人的プレゼントタイミングと相場の目安|失敗しない贈り物の選択
・退職プレゼント個人的にパートさんへ贈る感謝の品|相場&選び方とおすすめギフト
🎁 ぴったりの贈り物、簡単に見つかる!
>>シーンや相手に合わせた最適なプレゼントをサクッと検索。迷ったらこちら
▼忙しい日常に癒しの時間を▼